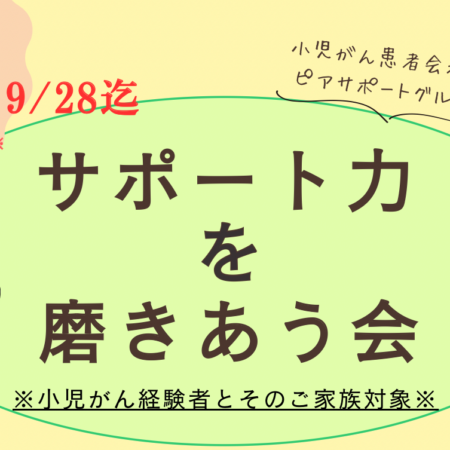小児がんとは、乳幼児から小児、思春期、若年成人に発生する悪性腫瘍の総称です。小児がんは、毎年2500名~3000名が罹患し、人口5000人~1万人に1人ほどの発症率であるといわれています(ただし、日本ではがん登録の整備が十分ではないため、これらはあくまで推計となっています)。
約3分の1が血液のがんである白血病とリンパ腫、残りが固形がんで、主なものでは脳腫瘍、神経芽細胞腫、ウィルムス腫瘍など、様々な種類があります。 小児固形がんは、胎児性組織から発生する芽腫(胎児性がん)と、成長過程の活発に増殖する細胞から発生する肉腫がほとんどであり、成人で一般的な上皮に発生する癌(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌など)とは種類も治療方針も異なります。また、生活習慣病ではないため、予防策を講じることは困難です。
成人の胃癌や肺癌は、それぞれ胃と肺にしか発生しませんが、小児固形がんの発生母地となる組織は体中至る所に存在するために、小児固形がんは体中のどこからでも発生するのが特徴です。そのため、診断病名は発生臓器別ではなく、病理組織学的に名付けられています。 また、化学療法や放射線療法が有効であるため、進行、転移のある患者さんでも、治癒を目指した治療が行われます。
乳幼児から小児期(0歳~15歳)、思春期(16歳~19歳)、若年成人(20歳以上)のどの年齢でも発症する可能性があるため、一部の患者さんは成人の診療科を受診されます。若年成人のリンパ腫や肉腫は、成人で一般的な治療を行うよりも、小児の治療方針で治療した方が成績は良いとされています。
医療の向上により、小児がんは現在70%~80%の方が治療に成功し、病気を制御することができるようになっていますが、依然として小児の病死原因の第1位を占めている一方、一旦治療に成功した後でも合併症や晩期の再発の危険を長期にわたってフォローする必要があります。
希少疾患でありながら、下記に示されるように種類が多種多様であり、発達期の幅広い年齢層で罹患することから、その診断と治療には非常に高い専門性が求められます。まず専門施設で正確な病理診断を受け、適切な初期治療を受けることが重要です。
国際小児がん分類 【主分類:12種類】
- 白血病、骨髄増殖性疾患、骨髄異形成症候群
- リンパ腫および網状内皮系腫瘍
- 中枢神経系および他の頭蓋内・脊髄内腫瘍
- 神経芽腫および他の末梢神経細胞腫瘍
- 網膜芽腫
- 腎腫瘍
- 肝腫瘍
- 悪性骨腫瘍
- 軟部肉腫および他の骨外発生の肉腫
- 胚細胞性腫瘍および他の性腺腫瘍
- 上皮性腫瘍および黒色腫
- その他および分類不能な上皮性癌
(Eva Steliarova・Foucher, et al. Cancer 2005;103:1457-67.)